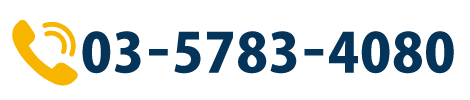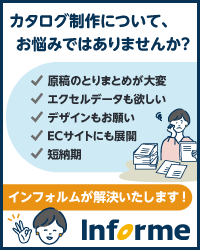印刷できない線
印刷で飛んでしまうオブジェクト
印刷にはいくつかの方法・種類がありますが、現在主流となっているのはオフセット印刷です。オフセット印刷の“オフセット”とは、原版(刷版)から直接紙にインクを印刷するのではなく、刷版からブランケットという別の素材にインクをいったん転写し、さらにそれを紙に再転写するということを意味しています。
このように転写を重ねても文字や線がきちんと想定された通りに印刷されるのは、オフセット印刷がそれだけ高度で精密な技術で成り立っているということでもあります。ただし、どんな場合でも完全に再現できるわけではありません。気をつけないとあるはずのものが印刷時に消えてしまうということもあり得るのです。
たとえば、平アミの濃度が低い場合、網点が飛んでしまい、印刷されないことがあります。最近はCTPが普及し、刷版がデータ通り正確に出力できるようになってきましたが、フィルムを出力してそれを刷版に焼きつけていたイメージセッタの時代は、1~2%レベルの網点を印刷で正確に再現するということはきわめて困難な作業でした。
175線で1%の網点となると0.01ミリ単位の世界です。印刷現場では、品質を安定させるためCTPや印刷機をはじめ、環境のデジタル管理などを進めていますが、それでも0.01ミリの小さな点を正確に印刷するのは簡単なことではありません。
一般に、平アミの濃度は低すぎないようにするべきであり、印刷が厳密に品質管理されている場合でも、1%や2%といった極端な指定はしないほうがいいでしょう。
注意が必要な線幅
平アミが印刷できちんと再現されないのも問題ですが、それ以上に問題になるのが、細い罫線などが飛んでしまうというトラブルです。特に図版の引き出し線などは消えてしまうと重大な事故につながります。
印刷で再現可能な線の幅は、一般に0.1ミリ程度が最低ラインとされています。要するにオモテ罫の太さです。トンボも0.1ミリ程度が一般的です。
これは、0.1ミリ未満の線だと必ず消えるということではありません。さまざまな印刷条件を考えた場合でも0.1ミリあればまず大丈夫ということですから、条件さえよければ0.04ミリでも0.03ミリでもきちんと印刷できるかもしれません。ただ、実際問題として、何ミリまでなら印刷可能かということをデータを作る側が事前に把握するのは、その印刷会社内部の制作部署でもなければ難しく、結局のところ、図版を作る場合は0.1ミリ未満の線を使わないようにしたほうが無難というわけです。
なお、Illustratorで塗りに色を指定して線幅を0にすると、線幅を持たない線、すなわちヘアラインになりますが、このヘアラインは、その出力機で出力できる最小幅の線で出力されるので注意が必要です。
また、図版を作る際は線幅に十分注意していても、そのあとでトラブルが起きるケースがあります。
たとえば、Illustratorで作成した図版をレイアウトソフトに貼り込んでレイアウトしたとします。その際、図版を100%で貼り込めばいいのですが、縮小して貼り込んだ場合は、線幅もそのまま縮小されることになります。
0.1ミリ幅で指定した線の図版を20%に縮小すれば線幅は0.02ミリとなり、印刷可能なレベルを下回ってしまいます。2,400dpiで出力したとして、0.02ミリはドット約2個分。印刷での正確な再現はなかなかシビアです。
プリンタ出力だと線の太さがきちんと確認できないというのが線幅の問題をさらに複雑にします。ヘアラインなど細い線を通常のプリンタから出力した場合、高解像度のCTPなどよりも太く出力されます。つまり、ゲラを見ただけでは線幅が印刷に適しているかどうか確認できないのです。
こういったトラブルを防止するためには、図版の線幅を基準より細くしない、図版をレイアウトソフトに貼り込む際はむやみに縮小しない、といったルールを守ることが大切です。
もちろん、データのチェックも重要です。それにはPDFを利用する方法が便利でしょう。Acrobatにはプリフライト機能が備わっています。この機能を使えばある基準より細い線がないかどうかをチェックできます。さらに、ヘアラインの線幅をコントロールする「ヘアラインを修正」機能を使って細い線を一律で適正な幅に変更することも可能です。
なお、細い線の印刷を考える場合、色の濃度についても考慮する必要があります。色の濃度が100%であれば、網点ではなく極小の出力ドットによって線が描画されます。2400dpiの出力機であれば0.01ミリのドットが集まって線となるわけです。一方、中間濃度だと網点になるため点と点の間が空き、線幅と濃度、角度によっては線がかすれたり点線に見えるといった問題が起きます。
色の掛け合わせが指定された線の幅をコントロールしたい場合は、プリフライト機能のフィックスアップでプロファイルを作って適用するということもできます。
細い線が印刷で飛んでしまうといった印刷工程で生じるトラブルは、データ制作工程でのチェックが難しいものですが、トラブルが起きた場合の重大性を考えると制作段階でしっかりと管理することが大切です。
(田村 2006.2.27初出)
(田村 2023.6.5更新)