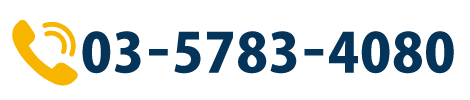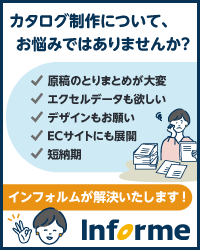文字間隔のコントロール
文字の間隔を適切に維持する
印刷物で、文字間隔を詰めて組まれた文を見かけることがよくあります。もともと、活字を並べて組む活版印刷では、文字の間隔を簡単に詰めることができず、ベタ組みか文字間隔を開けるしかありませんでした。写植の時代になり、自由に文字間隔をいじれるようになると、多くの印刷物で文字を詰めて組むツメ組みが流行しました。DTPでも、写植で培われた文字詰めを踏襲したレイアウトが少なくありません。
そもそも、なぜ文字の間隔を詰めるのでしょうか。タイトルや見出しの場合、文字と文字の間が開きすぎていると見る側が感じることがあります。日本語の文字はベタ組みだと等間隔に並びますが、文字が持つ本来の文字幅は文字ごとに違うので文字の組み合わせによっては間隔が広くなったり狭くなったりします。タイトルや大見出しのように文字サイズが大きい文だと文字間の空きが大きすぎてスカスカに見えることがあるのです。
こういった場合に、各文字の間隔を調整することで、読みやすさやバランスを向上させるために行われるのが文字詰めです。たとえば、横組みで、カタカナの「ノ」や「ク」「ト」、アラビア数字やアルファベットの「I」「L」など、文字の持つ幅が狭い文字の前後はどうしても他の文字の周りよりかなり空いて見えます。この場合、文字の間隔を詰めて空きが小さくなればスカスカな印象は解消され、読みやすさにもつながるでしょう。
InDesignには、文字間隔を詰める機能として、カーニングやトラッキング、文字ツメ、プロポーショナルメトリクスといった機能が用意されています。各文字間を手作業で詰めていくならカーニングや文字ツメでいいでしょうし、自動的に詰めを適用させるならプロポーショナルメトリクスやオプティカルカーニングなどが選択肢になります。ちなみに、プロポーショナルメトリクスは欧文に反映されないため、必要に応じてカーニング設定欄の「メトリクス」を指定します(A P-OTFフォントなどペアカーニング情報を持つフォントに効果)。
一方、本文の場合はちょっと事情が異なります。本文は文字サイズが小さく、文字数も多くなるのが普通です。1行や2行、文字数で数十字ですむタイトルや見出しと違い、本文を構成する文字は数千、数万字に及ぶこともあります。この場合、文字間の空きが広いかどうかは大きな文字ほど気にならないでしょう。むしろ文字間隔が詰まりすぎているほうが問題になりかねません。
実際の作業では、レイアウトデザイン的な要請で所定の行数に納めるために、文字間隔を詰めてあふれている文字を前の行に収めるといったこともよくあるわけですが、文字間隔を調整したために読みにくい、きれいでない組版になってしまうとすれば、組版設計に問題があった可能性も考えられます。
組版を設計する場合、文字のサイズと共に行の長さ(コラム幅)を決めなければなりません。DTPが普及したことで、テキストボックスの大きさをオペレーターが簡単にコントロールできるようになりましたが、そのために適切な行長をきちんと考えずにいい加減な設定をしてしまうケースも少なくないようです。
文字サイズに対して行長がある程度以上ないと、文字を詰めた際に詰まりすぎて可読性を損ないます。逆に、行長が長すぎても読み手の目が改行の際に行を間違えるリスクが大きくなり可読性が低下します。適切な行長が重要なのです。
また、行長によっては、文字をベタに組んでも行にピッタリと収まらず、半端になります。行末に文字を揃える場合、都合よく行中に約物があればそこで詰めて調整すればいいわけですが、なければ文字間隔で調整するしかありません。スカスカに見えないように文字間隔を詰め気味にすると今度は詰まりすぎて可読性の悪い組版になってしまうということもあります。
では、適切な行長にするにはどうすればいいのでしょうか。1行あたりの適切な文字数は、文章の内容によって違ってきます。たとえば、古典文学本と、英単語や数字が頻繁に出てくる技術書とでは、適した行長は違って当然でしょう。すべてが漢字とかなで構成される文章なら比較的行長が短くても問題は起きにくいかもしれませんが、英単語、特に長い固有名詞が頻発するような文章で行長が短いと文字間隔を適切に維持するのが極めて困難になります。
また、余計な文字間隔の調整を生じさせないためには、ベタ組みにして行にピッタリ収まる行長がベターです。そのため、行長が文字サイズの倍数になるよう調整します。たとえば、文字サイズが12級で横一行に文字を20字収めたいのであれば、3ミリ(12級)×20=60ミリ、つまり60ミリの幅のテキストボックスを作り、そこに流し込めばいいことになります。
もちろん、このように厳密に計算して行長を決めたとしても、約物の連続や行末の禁則、あるいはアルファベットや数字など行を全角ベタで組めないケースがあるので常に適切な文字間隔が実現できるわけではありません。それでも、行長が適切でなければほとんどの文字間隔で(文字詰めなどの)処理が必要になるのに対して、適切であれば例外的な部分だけを処理すればいいわけで、その優劣はおのずから明らかでしょう。
なお、InDesignの場合、適切な行長を簡単に指定できるフレームグリッドを使えば、面倒な計算は不要です。プレーンなテキストフレームだと、計算しないときちんとした行長は出せませんし、また、フレームグリッドであっても、文字サイズが設定と異なる場合や、インデントなどで行長が変わってくる場合は、文字サイズと行長の関係を考慮して指定を行う必要があります。
また、表の組版でも同じような問題が起きがちです。表の場合、十分な行長を取れないことが多く、どうしても文字が空き気味になったり詰まり気味になったりします。この場合も、文字サイズとセルの幅を考慮して適切な行長を割り出し、その行長になるようにセルのマージンを調整する必要があるわけです。
文字間隔を空ける処理
日本語の組版では、名前リストなどで文字間隔を空けて組み、文字列の幅を合わせることがよくあります。そういった場合、文字と文字の間に全角や半角スペースを入れて組むことが多いようです。確かに、スペースを入力して合わせる方法は手軽にできて便利な面もありますが、数が多くなると面倒ですし、文字列の幅が変更になったら全部をひとつずつ変更しなければなりません。
また、DTPデータをWebやデータベースに流用するといった場合は、スペースが邪魔になることもあります。とはいえ、カーニングや字送りといった機能を使うにしてもひとつずつ指定するのは同じですし手間も変わりません。
InDesignには、こういった場合に便利な「字取り」という機能が用意されています。この機能は、選択した文字列の幅を指定した字数に合わせて調整するというもので、たとえば5文字の文字列に「10」の字取りを適用すると、自動的に文字間隔を広げて10文字分の幅にしてくれます。
この機能は便利な機能ですが、ひとつ問題があります。それは、この機能がフレームグリッドを前提にした機能であるという点です。フレームグリッドで字取りを使った場合、そのフレームグリッドに指定されている文字サイズを基準に、その文字サイズ×指定した数で文字列の幅がコントロールされます。基準となる文字サイズを変更したければ、フレームグリッド設定を開き、書式属性の文字サイズを変更します。
ところが、プレーンなテキストフレームの場合、フレームグリッド設定はありません。文字列のサイズを変更しても字取りで基準となっている文字サイズは変更されず、通常は13級を基準に字取りされてしまいます。
実は、InDesignではプレーンなテキストフレームにもフレームグリッド設定の文字サイズの情報が保持されていて(デフォルトは13級)、それが字取り機能を使う際に効いてくるのです。
プレーンなテキストフレームで字取り機能を使う場合、テキストフレームに隠されているフレームグリッド設定の文字サイズを変更しなければなりません。そのためには、いったんフレームの種類をフレームグリッドに変更し、そこで文字サイズを適切な数値に書き換え、さらにフレームの種類をテキストフレームに戻すという作業が必要です。
この作業を行うことで、テキストフレームに隠されている文字サイズ設定が変更でき、思ったとおりの文字サイズを規準に字取りを行うことができるようになります。
なお、いったんフレームグリッドに変更することで、フレームの幅や文字の設定などが変わってしまい、テキストフレームに戻した際に調整し直すといった手間が生じるかもしれませんので、このデメリットと字取り機能が使えるというメリットを比べて処理を決めるべきでしょう。
(田村 2008.7.7初出)
(田村 2025.5.8更新)