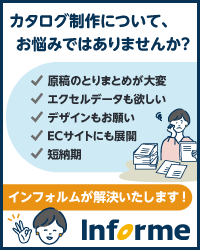PDFのオーバープリントに注意
オーバープリントの乱用は危険
InDesignやIllustratorなどのDTPアプリケーションには、オブジェクトに「オーバープリント」という属性を指定する機能が備わっています。オーバープリントは、オブジェクトが重なっている場合に、上のオブジェクトを透かして下のオブジェクトの色も見えるように印刷するというものです。たとえば上のオブジェクトがシアン80%、下のオブジェクトがマゼンタ100%で、上のオブジェクトをオーバープリントに指定すると、重なった部分がC80%M100%の掛け合わせになるわけです。
なお、オーバープリントは分版出力する際に処理が行われるため、制作したアプリケーションの画面上や通常のプリンタ出力時にはオーバープリントされていないのと同じ状態になります。
最近は透明効果が使われるようになり、オーバープリントとの違いが分かりにくくなっていますが、オーバープリントは、上のオブジェクトの色を構成するカラー(フルカラーであればCMYKの4版)で、濃度がないチャンネルにおいてだけ下の色が透けて印刷されるという処理が行われます。同様のケースで、上のオブジェクトがC80%M1%だった場合は、1%でもデータがあるマゼンタチャンネルは下の100%が透けることなく、上の1%だけが印刷されます。この場合はオーバープリントを指定するしないに関係なく、印刷では(ほぼ)シアン単色に見えるはずです。
このように、オーバープリントという処理はチャンネルのデータ次第で色が大きく変わるにもかかわらず、通常のプリンタではオーバープリントが再現されない状態で出力されて作業者の確認ミスを誘発するため、むやみに使うのは危険です。一般的なDTP作業でオーバープリントが必要なのは、特色との掛け合わせや版ズレを防止する目的で文字など墨ベタを下の色に乗せる場合くらいで、それ以外は極力使わないようにするべきでしょう。
とはいえ、実際のDTPでは、意味もなくオーバープリントが指定されたデータが出力に回ってくるケースも少なくありません。そのため、出力現場では、仕様書で指定されていない限り、RIPの機能を使って墨ベタと特色以外のオーバープリントの指定を解除して出力するということもよく行われていました。スミベタや特色以外のオブジェクトでオーバープリントが指定されている場合、制作したオペレーターはオーバープリントの指定をしたことに気づかずにデータを作っていることが多く、そのままオーバープリントで出力すると、クライアントが意図していない色になってかえってトラブルになる危険すらありました。
DTPでは、データで指定されたものがそのまま出力されるというのが原則ですが、オーバープリントに限っては出力オペレーターの操作に依存するあいまいさがあり、注意が必要です。
PDFのカラー定義
Acrobatのプリフライト機能を使っていると、同じようなオブジェクトでも、色にはDeviceCMYK、Separation、DeviceNといった種類があることに気付きます。
「DeviceCMYK」というのは、CMYKの4つ全てのチャンネルのパーセントが指定されたカラーです。この場合、シアンにしか色がなくても、他の3つのチャンネルにも「0」という数値が与えられています。これが一般的な4色CMYKデータです。
一方、「Separation」というのは通常特色の版で使われるカラーで、基本的に単色しか扱えません。DeviceCMYKというカラースペースはCMYKの4チャンネルの値しか使えないため、特色を扱うためにこの色定義が必要になったのですが、実際には特色だけでなく、CMYKの1色を表現する場合にも使えます。
たとえば、K版だけのオブジェクトに対して、DeviceCMYKで「0,0,0,100」などと定義するのではなく、Separationで「Black=100」のように定義することも可能なのです。この場合、このオブジェクトにはCMYの各チャンネルは“存在しない”ことになります。
次に、「DeviceN」というのはPostScript 3およびPDF1.3以降で使われるようになったカラー定義で、CMYKも特色も同じように扱え、多色印刷にも対応できます。
DeviceNでは、色のチャンネル数は決まっていません。定義すればどのようなチャンネルも含めることができるのです(定義できるチャンネル数の上限は、PDF1.3で8色、PDF1.5では32色)。たとえば、「(特色)DIC 202,(特色)Cyan,(特色)Yellow=50,25,100」というように、CMYKと特色の掛け合わせも問題なく可能です。
InDesignでは、混合インキスウォッチで特色同士やプロセスカラーと特色の掛け合わせを指定できますが、この混合インキスウォッチで指定された色はDeviceNで表現されることになります。
DeviceNでは、必要な色だけを定義することができます。たとえば、上記の例のようにシアンとイエロー、プラス特色の合計3チャンネルが定義されたDeviceNのオブジェクトには、マゼンタやブラックのチャンネルが“存在しない”のです。
カラー定義の変換
DeviceCMYKとSeparation、DeviceNの最大の違いは色数です。DeviceCMYKは(たとえ0%であっても)必ずCMYKの4つのチャンネルでなければならないのに対して、Separationは1つだけ、DeviceNはチャンネルはいくつでも定義できますし、CMYKが揃っている必要もありません。
これがオーバープリント処理で重要なポイントになります。実は従来はRIPによって通常のDeviceCMYKだとオーバープリント処理されない場合があったのです。
DeviceCMYKをオーバープリント処理するには、上のオブジェクトで0%のチャンネルがあればそれをパスして下の色を使うということになります。ところが、Adobe純正RIPの基本的な仕様だと、0%のチャンネルはたとえオーバープリントの指定があってもパスされませんでした。つまり、DeviceCMYK同士は本来オーバープリント処理できなかったのです。Adobe純正RIPの仕組みでは、上のオブジェクトにSeparationを使うなどでチャンネルそのものがない状態がオーバープリント処理の前提条件だったわけです。
そのため、各RIPはそれぞれ独自の機能を追加してDeviceCMYKの0%チャンネルで下の色が使えるようにしていました。ただし、これはあくまでも各RIPに依存するものでした。
PDFではDeviceCMYKオブジェクトに「OPM」という属性が指定できるようになっています。OPMとはオーバープリントモードのことで、オーバープリントが指定されたCMYKオブジェクトのオーバープリント処理をコントロールするための属性です。
OPMには0と1の2つのモードがあります。DeviceCMYKオブジェクト同士が重なっていて、上に乗っているオブジェクトにOPM 0が指定されている場合、0%のチャンネルは0%として出力されます。つまり、オーバープリントの処理は行われません。
上のオブジェクトにOPM 1が適用されていれば、0%のチャンネルは無視して下の色を出力する、つまりオーバープリントが適用されることになります。ちなみに、Distillerの「詳細設定」で「オーバープリントのデフォルトをノンゼロオーバープリントにする」にチェックが入っているとPDF全体にOPM 1が適用されます。現在、AdobeアプリケーションからPDFを書き出す場合は、OPM 1がデフォルトです。
オーバープリントの問題
PDFの規格では、DeviceCMYKオブジェクトが下にあり、その上に配置されたオブジェクトがDeviceCMYKのグラデーションやパターン、画像、またはDeviceGrayだった場合、オーバープリント処理は行われないとなっています。
実際、PDFの直接出力が可能なAdobe PDF Print Engine(APPE)搭載RIPでは、これらのデータはオーバープリントされません。ただし、APPEではないRIPはその限りではありませんし、PSを出力する場合も同様です。
最近のAdobe製DTPアプリケーションでは、PDF出力時に、出力形態や環境などによる齟齬が生じないようなカラースペースが使用されるようになっています。
たとえば、DeviceCMYKオブジェクトの上にあるグラデーションオブジェクトにオーバープリントの指定をすると、PDFではグラデーションのカラースペースがDeviceCMYKではなくDeviceNで出力されます。DeviceNのオブジェクトであれば、上記の制約は生じず、オーバープリント処理が行われます。
また、以前はIllustratorなどでグレースケールの色を指定した場合にDeviceGrayのカラースペースに書き出されていましたが、最近のAdobe製アプリケーションはグレースケールの指定でもDeviceGrayにならずDeviceCMYKで書き出されるようになっています。
画像に関しては、Illustratorでオーバープリントが指定されていてもオーバープリントになりません(InDesignは画像に対するオーバープリント指定そのものができないようになっている)。この点は指定と実際の処理が異なるので注意が必要でしょう。
もっとも、そもそもグラデーションやパターン、画像にオーバープリントを指定するというニーズそのものが実際にはあまり考えられないことから、この問題はそれほど気にしなくてもいいのかもしれません。
ただし、もし、スミベタや特色以外にオーバープリントをどうしても使いたいということがあれば、オーバープリントよりも透明効果の活用を考えてみるほうがよさそうです。
(田村 2008.10.20初出)
(田村 2022.11.15更新)