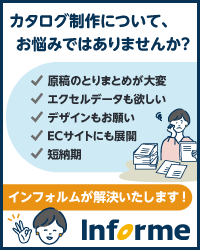表記の論理を整理しよう
表記法に潜む論理
印刷物の読みやすさを考えた場合、文章の表記法が重要な要素になります。同じ印刷物の中で異なる表記ルールが混在しているとよくないのはもちろんですが、別の印刷物であっても言語が同じであれば同じ表記ルールで記述されていたほうが読み手にとってもいいはずです。ところが、言語の表記法というのは法律できちんと定められているわけではなく、慣例的に作り上げられてきたものであるため、一般的な表記法に則っていない独自の表記ルールになっていたり、ルール自体に矛盾があるような印刷物もしばしば見られます。
もちろん慣例的な表記ルールが正しいとは限らないのですが、先人が積み重ねてきたルールには論理的な裏づけがあるものが多く、慣例的な表記法に従わなかったために論理的におかしな表記になっていることも少なくないようです。逆に言うと、表記法を考える場合には、それがどのような論理によって支えられ裏付けられているかを考える必要があるということになります。今回は問題になりやすい表記法とその裏づけとなる論理について考えてみましょう。
桁区切りのカンマ
大きい数字を書いたり読んだりする場合、桁数を一つずつ数えないと読めないというのでは面倒です。そういった際に、桁を間違えないようにするためにいくつかの桁ごとにカンマなどの記号を入れて位取りの目安とすることが日本では一般に行われています。
この記号はあくまで目安であり、数値そのものには影響しないため、どのように入れてもいいようなものですが、現在では3桁ごとに記号を入れるというのが一般的です。ただし、日本には4桁ごとに記号を入れるルールもあり、実際、工業製品における日本語組版ルールを扱った「JIS X 4051」には3桁および4桁ごとに入れるとされています。
3桁ごとに入れるのは、おそらく欧米語で3桁が位取りの単位として多く使われているからでしょう。たとえばアメリカ英語では1,000がthousand、1,000,000がmillion、1,000,000,000がbillionといったように3桁ごとに数詞が変わります(イギリス英語は1,000,000,000以降の単位語が違っていたが最近はアメリカ英語に合わせることが多い)。実際、3桁ごとにカンマが入ることで、10桁以上の数字でも比較的楽に読めるのは事実です。
ところで、日本語には4桁ごとに「万」「億」「兆」といった位取りを表す数詞を使います。数字を読み上げる場合、あるいは漢数字を使う場合はもちろんですが、印刷物でアラビア数字を使った場合でも「1132兆5120億8300万円」といったようにこれらの数詞を入れることがあり、その場合に3桁ごとに入れるカンマとの整合性が問題になります。
カンマも数詞も、位取りを表すという意味では同じ役割を持っています。しかし、片方は3桁ずつ、もう一方は4桁ずつと、入る位置が微妙に異なります。
こういったケースで、4桁ごとに数詞を使い、さらに3桁めと4桁めの数字の間にカンマを使っている例をよく見かけます(例:1億5,250万3,320円)。一見問題ないように思われるかもしれませんが、よく考えてみると、数詞とカンマはどちらも同じ役割を持つものです。わざわざダブって使う意味があるのでしょうか。
日本語の数詞は4桁ごとに入るため、基本的に数字が5桁以上連なることはありません。ということは、3桁ごとに区切るカンマには千の位と百の位を分けるという意味しかないわけです。4桁の数字で千の位と百の位をカンマで区別する必要があるかというと、一般的にはまずないでしょう。実際に比べてみれば分かりますが、カンマはなくても読み取りに支障がなく、むしろ煩わしく感じることさえあるはずです。
前出のJIS X 4051でも、位取りの数詞(単位語)とカンマは混在しないと明記してあります。
ちなみに、日本や英米などでは、小数点の記号にピリオド、桁の位取りの記号にカンマを使います(例:2,123,321.5)が、世界的に見ると、ピリオドを位取り、カンマを小数点に使う(例:2.123.321,5)国も多く、特にヨーロッパはイギリス以外ほとんどが小数点にカンマを使っています(日本で小数点付き数字を読み上げる際に「れいコンマいち」などというのはこの影響らしい)。中にはISOやIECなどのように、小数点にカンマを使うことを指針で定めている国際機関もあります。
世界的に統一されていないのは何と言っても不便でもあり、2003年に開かれた第22回国際度量衡総会では統一に向けての議論がなされましたが、結論として「小数点はカンマかピリオドのどちらかを使う。桁の位取りはピリオドもカンマも使わず、半角スペースを入れる」ということになりました。要するに統一できなかったわけですが、英語以外の言語で数字を表記する場合は注意が必要です。
括弧と句読点
かぎ括弧やパーレンなどが文末や文の区切り目、つまり句読点が入る位置にくる場合、括弧と句読点の関係をどうするかというのも問題になりやすい点です。
たとえば、
1 「私は要りません。」「では彼にあげましょう。」
2 それがいわゆる「不要不急」ということでしょう。
3 彼は「それは要らない」と言った。
4 それは要らない(彼の言葉)。
5 それは要らない。(これは以前彼が自ら言っていたことだ。)
1の文章では、かぎ括弧の中で文が完結しています。2はかぎ括弧の中が引用語です。3はかぎ括弧内でひとつの文ですが、全体の文に組み込まれています。4は、文章の最後に補足する語句がパーレンで入り、その後に句点がきています。5では、文はいったん完結していて、さらにパーレンで囲まれた文章が追加されています。
こういった場合、句読点が必要なのかどうか、また、入れるとすればどこに入れるかが問題になります。
学校では、かぎ括弧の前に句読点をつけるように指導されていますが、これは昭和21年に作られた「くぎり符号の使ひ方[句読法](案)」をその論拠としているようです。そこには、
句点は
・「 」の中でも文の終止には打つ (1)
・引用語には打たない (2)
・引用語の内容が文の形式をなしていても簡単なものには打たない (3)
・文の終止で、カッコをへだてて打つことがある (4)
・付記的な一節を全部カッコで囲む場合には、その中にマルが入る (5)
などと書かれています。
上記の例文は、この句読法に即しているわけですが、実際の印刷物、特に小説では閉じるかぎ括弧の前には句点を入れないことが多いようです。これは、現実問題として、かぎ括弧でくくってあれば句点を入れなくても切れ目が判別できるというのが大きな理由でしょう。
また、4と5の違いが微妙なケースもあるでしょう。5では、閉じ括弧の前の句点を取ったり、括弧の後に句点を付けるというものも実際の例では見られます。
これらを考えてみると、括弧と句読点が両方使われている場合に片方を省略できるかどうかというのがポイントのようです。どちらも文の区切りを示す記号であるため、片方だけでも区切りは付けられます。ただし、厳密に言えば意味は異なるわけで、それをあえて際立たせたいのであれば、句読点を律儀に付けるということになるでしょう。
文章において、表記法は単に見た目をよくするだけでなく、読み手に文章の論理構造を正確に伝えるという重要な役割を担っています。表記ルールを決める際は、適当に決めるのではなく、よくその意味合いを考えた上で定めることが大切ではないでしょうか。
(田村 2010.3.8初出)
(田村 2023.1.23更新)